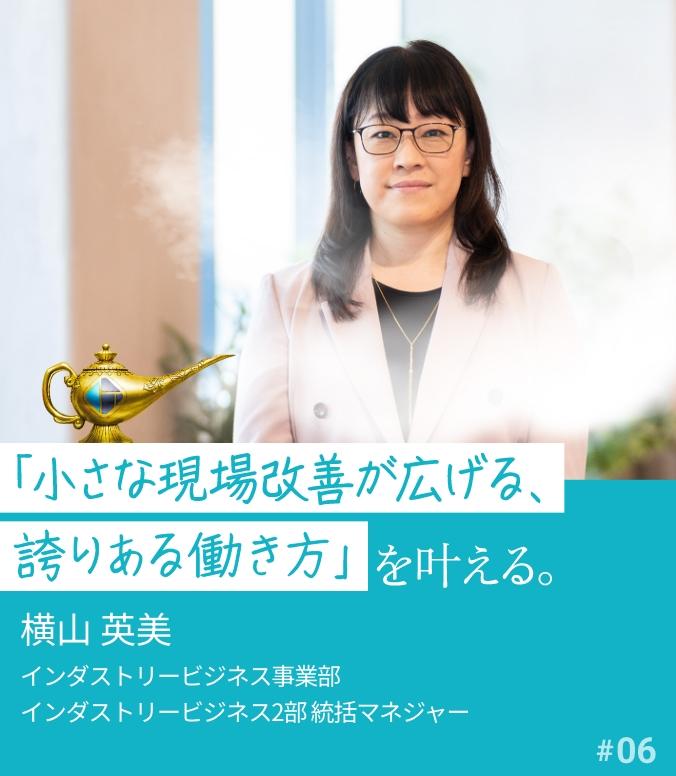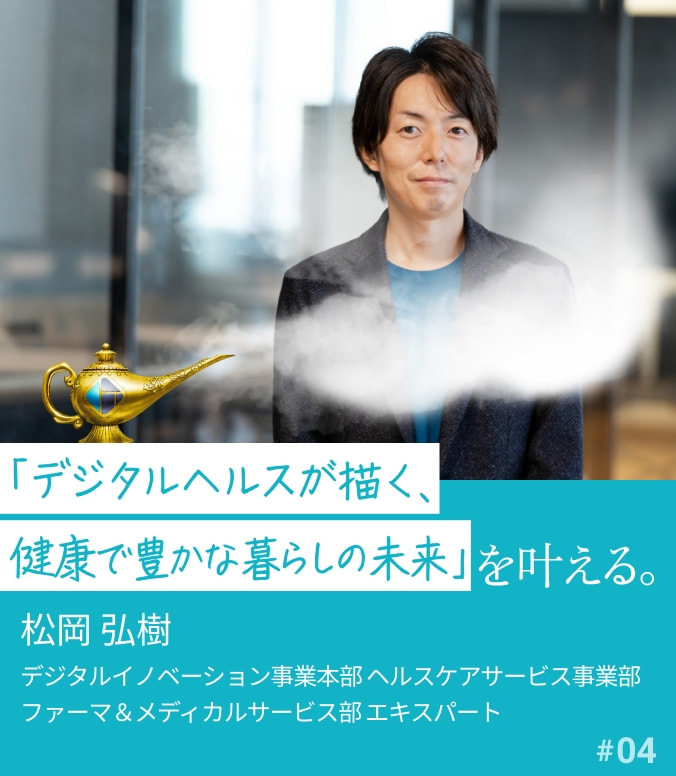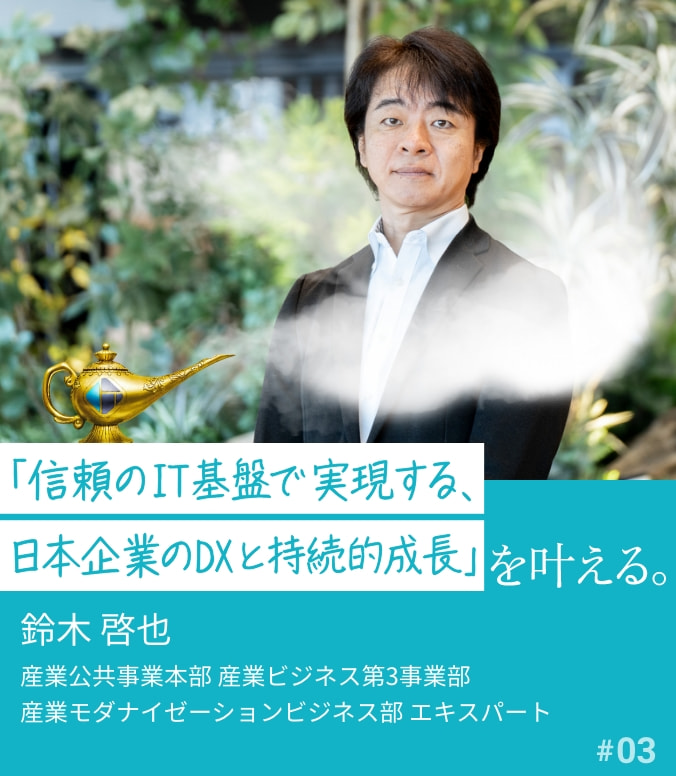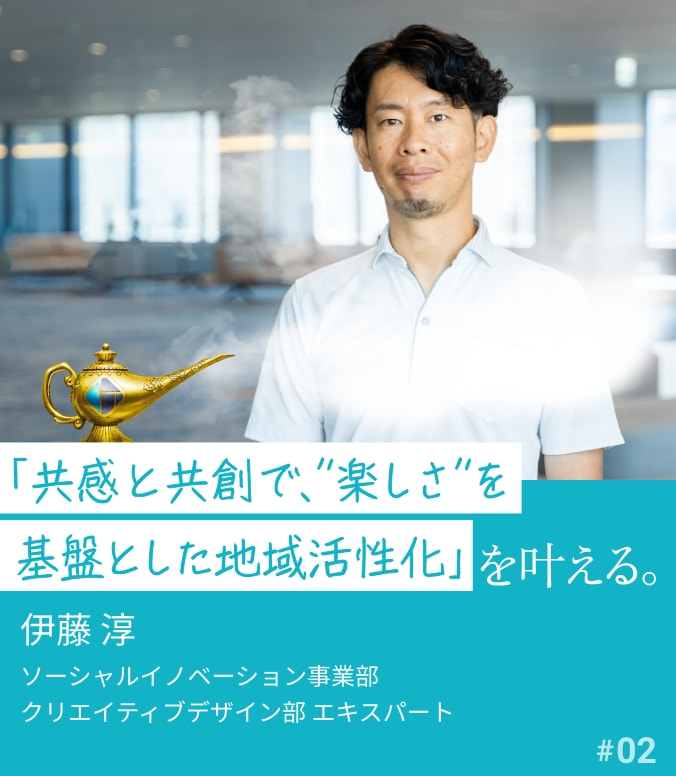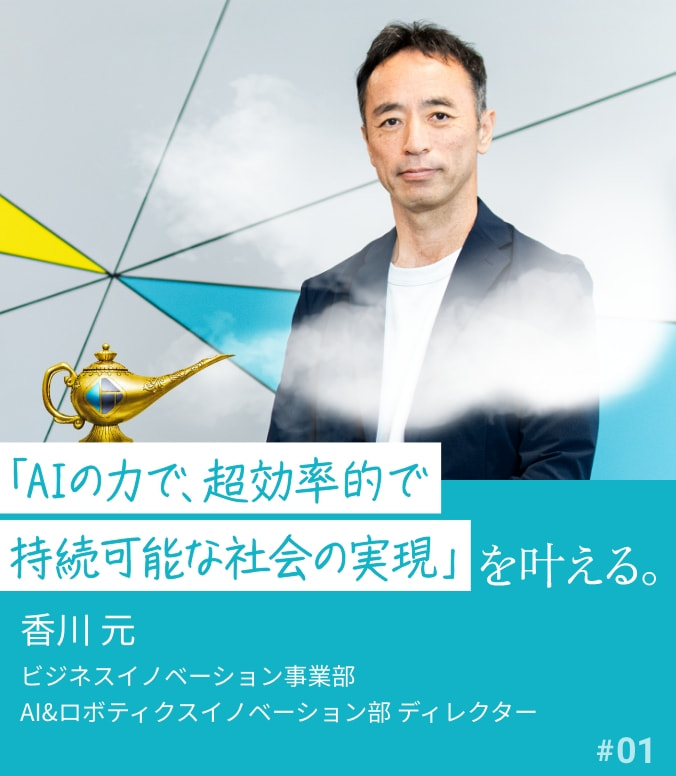#05
#05
野田 将大Shota Noda
TIS株式会社 ビジネスイノベーション事業部 ストラテジー&イノベーションコンサルティング部 コンサルタント
2024年入社。現在は自動運転をテーマとした新規事業の立ち上げを担当。自動運転メーカーとの合弁会社「ピクセルインテリジェンス株式会社」と連携し、自動運転などのモビリティ領域にITやAI技術を融合させ、新たな社会価値の創出に挑んでいる。中でも、モビリティによって、人々の暮らしの質を高め、地方の人手不足や高齢者の移動支援といった社会課題の解決に繋げる取り組みを推進している。
2024年入社。現在は自動運転をテーマとした新規事業の立ち上げを担当。自動運転メーカーとの合弁会社「ピクセルインテリジェンス株式会社」と連携し、自動運転などのモビリティ領域にITやAI技術を融合させ、新たな社会価値の創出に挑んでいる。中でも、モビリティによって、人々の暮らしの質を高め、地方の人手不足や高齢者の移動支援といった社会課題の解決に繋げる取り組みを推進している。


「TISの様々な強みを掛け合わせて、ワクワクする未来を実現したい」と語るのは、TISのビジネスイノベーション事業部 ストラテジー&イノベーションコンサルティング部のコンサルタント、野田 将大。
自動運転というモビリティ領域に、ITやAI技術を掛け合わせることで新たな価値を創出し、誰もが必要なときに安心して移動できる社会の実現を目指しています。移動に制約を抱える高齢者や、買い物に困る過疎地の生活者を支える、新たなモビリティの形とは──。本記事では、その野田の取り組みと自動運転(モビリティ)技術がもたらす未来の社会像に迫ります。
モビリティが築く、地域と繋がる未来のインフラ
現在取り組んでいるお仕事の中で、ご自身が叶えたいと思っている願いは何でしょうか?
私が叶えたい願いは、「誰もが・いつでも・どこでも」安心で快適に暮らせる社会を、モビリティの力で実現することです。現在は、そうした社会の実現に向けて、モビリティを活用した新しいサービスの立ち上げに取り組んでいます。
将来的には、無人タクシーや移動販売車など、日常生活を支えるサービスを必要なときに利用できる社会をつくっていきたいと考えています。例えば、高齢の方や子育て中の家庭が、病院や買い物先へ気軽に行ける無人タクシー、スーパーに行くことが難しい地域や家庭に日用品や食料品を届ける移動販売車などです。その他にも、移動型クリニックや災害時の支援モビリティなど、様々な形で応用できると思います。
このように、モビリティの活用は、単なる利便性の向上にとどまらず、地域全体の暮らしやすさを支える重要な基盤になると考えています。MaaS(Mobility as a Service)(※1)領域を中心に、未来の暮らしをもっと便利に、もっとワクワクするものへと変えていくことが、今の私の願いです。
※1 MaaS(Mobility as a Service):個人の移動ニーズに対応して、複数の公共交通や民間の移動サービスを組み合わせ、検索・予約・決済などを一括で行うサービス。目的地における交通以外のサービスと連携することで地域の課題解決にも貢献する。

その願いを抱いたきっかけや背景があれば教えていただけますか?
地方の観光地や宿泊施設では、従業員の人員確保や来訪者・宿泊者へのサービス品質の維持といった深刻な課題に直面しています。移動手段の提供、現地での接客や荷物の運搬など、日々の業務の多くが慢性的な人手不足の中で行われているのが実情です。
こうした地域に根差した社会課題に対して、「ITの力で何かできるのではないか」という想いを抱くようになりました。前職ではコンサルタントとして、社会やビジネスの構造的な課題に向き合ってきましたが、その経験から、現場のリアルとIT・テクノロジーをどう繋ぐかが、本質的な課題解決の鍵になると感じています。
TISではこれまで、ソフトウェアを中心とした新規事業開発に取り組んできましたが、今回はそこから一歩踏み出し、ハードウェアであるモビリティを活用した新たな価値創出に挑戦しています。その一環として、自動運転EVや各種ロボットを開発する株式会社ピクシームービングと合弁会社「ピクセルインテリジェンス株式会社」を設立し、TISが持つAIやデータ分析などの技術と掛け合わせながら、新しいサービスの社会実装を進めています。
無人モビリティを人手不足の現場に導入することで、移動やサービス提供の支援はもちろん、利用者の体験価値の向上や業務の効率化にも繋がると考えています。さらに、「車両」という目に見える形で社会に価値を届けられるという実感が、この取り組みを進める大きなモチベーションになっています。
ブランドの世界観を乗せて走る、体験価値の最前線
ご自身が叶えたいと考えている願いに対して、どのような形で取り組まれていますか?
現在は、「ブランドエクスペリエンス“ポップアップ”モビリティ」という、無人自動運転車両とAIを活用した新たなサービスを開発しています。このプロジェクトでは、車両全体を特定ブランドの世界観に合わせてデザインし、移動型のブランド体験を提供することを目指しています。
2025年3月に実施した実証実験では、ウェルビーイングブランド「Cycle.me」と連携し、同ブランドの世界観に没入できる専用デザインを施したモビリティ「Robo-Shop」を活用しました。体験者の方々には、車内で「Cycle.me」の各商品の香りを実際に体験していただきながら、イヤホン型の脳波計を装着して脳波を測定。そのデータをもとに、AIが一人ひとりに合った商品をレコメンドするという内容です。

体験に参加された方の9割以上からは、「ワクワクした」「新しさを感じた」「ブランドへの理解や好意が深まった」といった肯定的な声をいただきました。モビリティを通じた新しい形のブランド体験が、社会に受け入れられる可能性を感じた手応えのある取り組みとなりました。

それらの取り組みの中で、困難に感じる部分はありますか?
新しい領域だからこその難しさは、やはり多くあります。自動運転に関する法規制をはじめ、車両の開発や改装、設置場所の調整など、乗り越えるべき課題は多岐にわたりました。
特に、今回のように前例の少ない取り組みでは、地域や土地の管理者との連携など、サービス開発以外の対応も求められます。例えば、公道で自動運転車両を走行させるためには、地方運輸局との事前調整を経た上で、国土交通省からの許可を得る必要があります。設置場所についても、土地・施設の管理者からの許可に加え、動線などを踏まえた計画書の提出が求められるなど、様々な調整が必要です。
また、自動運転の安全性については、まだ多くの懸念や不安の声もあり、理解を得るための対話が欠かせません。
だからこそ私たちは、車両やシステムの開発、法令遵守といった技術的・制度的な対応にとどまらず、地域の方々や関係機関との丁寧な対話を重ねながら、社会に信頼されるサービスの実現を目指しています。
ご自身の職務を果たす上で、どういった部分にやりがいを感じますか?
自分たちが描いたアイデアが、「Robo-Shop」というモビリティの形として実現し、実際に街中を走っているのを目にしたとき、大きなやりがいを感じました。さらに、実証実験の現場では、実際に車両を訪れた方々のワクワクした表情や、驚き、喜びといった反応を間近で見ることができ、それも大きな励みになりました。
実証実験の体験後アンケートでは、車内の演出と一連の体験を魅力と感じた参加者が97%にのぼり、また95%が「Cycle.me」への理解が深まった、または好感を持ったと回答しました。さらに、購入意欲も85%と高い評価をいただくことができました。
「Robo-Shop」での没入体験や、AIによるレコメンドを通じて、ブランドの世界観をより深く伝えることができたと感じています。私たちの取り組みが、しっかりと社会に価値を届けられている。その実感こそが、何よりのやりがいになっています。

IT×〇〇で広がる、新しい社会インフラの可能性
今後、どのような領域、どのような関わり方で社会課題解決に貢献していきたいとお考えですか?
今後は、TISの持つ多様な技術や知見を掛け合わせながら、より広い領域で社会に新しい価値を届けていきたいと考えています。例えば、AIやロボティクス、金融・決済といった分野に強みを持つ社内の専門部門と連携し、「自動運転×IT」にとどまらず、「〇〇×IT」「〇〇×AI」など、様々な掛け合わせによって、これまでにない価値の創出に挑戦していきたいです。
また、実証実験の域を超えて、事業としての持続性と社会からの受容性の両立を目指しながら、サービスを広く展開していくことがこれからの目標です。例えば、「自動運転×IT」の力で、高齢者の移動支援や過疎地域での交通手段の確保、さらには物流の効率化といった、多様な社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。
そのためにもまずは、自分自身が構想力と実行力の両方を備えたコンサルタントとして成長し、TISの中核を担う人材へとステップアップしていく必要があると感じています。モビリティを起点に、TISの技術と人の力を繋ぎ、「まだ見ぬ未来」を形にしていく。そんな挑戦を、これからも一歩ずつ、着実に形にしていきたいと思っています。
※本記事の内容は、2025年7月28日時点のものです。

TISインテックグループ社員と
外部有識者の方が対談を行うコーナーです。
社会課題の解決のために
叶えたい願いと想いを語るコーナーです。

タイアップ記事をご紹介します。

TISインテックグループの
取り組みについて発信するWEBマガジン