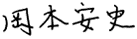トップメッセージ(統合報告書版)
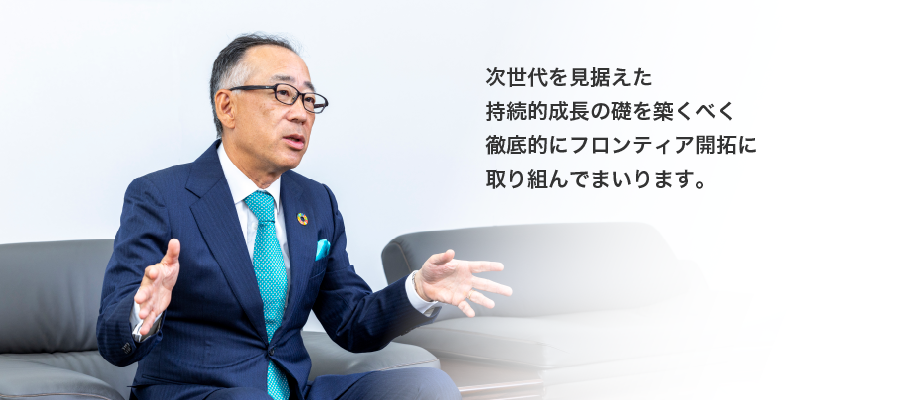
次の10年に向けて私たちにはさらなる進化が必要です。
2024年4月、当社グループは「グループビジョン2032」とその実現に向けたファーストステージである中期経営計画(2024-2026)をスタートさせました。
前中期経営計画では、デジタル化の加速を追い風に、コロナ禍を乗り越えて着実に成長を遂げてきました。しかし、社会を取り巻く環境は依然として不透明な状況が続いており、あらためてこれからの将来を見通すことが非常に困難な時代になったと感じています。
また、技術革新はこれまでにも増して加速度的に進んでおり、特にAIはかつてインターネットが社会変革をもたらしたように、社会に根差した技術として進化しつつあります。さらに量子コンピュータの進化など、今後はビジネスモデルや社会のあり方を変えうるテクノロジーが次々と実用段階に入り、ますますITの力が社会に不可分となってきます。こういった状況の中で成長を続けるには、今を冷静に分析しながらこれからの社会に不可分なITをしっかりとビジネス化する、柔軟性と適用力がこれまで以上に重要になってくるというのが私の考えです。
新しいスタートにおいては、今までやってきたことの延長線だけでなく、社会やお客様との対話を通してニーズをいち早く捉え、フロンティア開拓の基本方針のもと、新しい挑戦に向けて一歩を踏み出していく、そんな意識を我々一人ひとりが持って取り組んでいかなければならないと思っています。もちろんその根底として「OUR PHILOSOPHY」を変わらない我々の価値観として堅持していくのは当然のことです。
前中期経営計画では大きな成果を挙げる一方で、課題も残りました。
前中期経営計画で掲げた重要経営指標については、その多くを2023年3月期に1年前倒しで目標を達成する等、しっかりと向上させることができました。また、こうした成果の原動力となった従業員の頑張りに報いるという経営の責務を果たすために報酬の引き上げも継続的に実現しました。定性面でもサステナビリティ経営の高度化をはじめ、フロントライン強化の実現を支えるコンサルタントの拡充、タイのMFECを中心としたグローバル事業の拡大等、全体としては着実に進捗したと考えています。一方で、課題として残ったのは、ITオファリングサービス(IOS)の立ち上がりや収益性向上に想定よりも時間がかかっていることです。
当社グループは、現在も進化を続けているデジタル決済プラットフォーム「PAYCIERGE(ペイシェルジュ)」に基づくペイメント事業戦略をIOS成長の牽引役として位置付けています。この3年を振り返ると、クレジットSaaS(正式名称はクレジットカードプロセッシングサービス)がサービスインできたこと、今後の中長期的な成長を見据えた積極的な投資による機能拡充が進んだことはIOSの事業規模拡大に大きく貢献しました。しかしながら、リカーリング比率が大きく高まる状況にはまだ至らず、収益性の点では期待通りの成長とはなりませんでした。スマートフォンの普及を通じたデジタル口座ニーズが増加し、よりライトな決済ニーズが急速に広がっていること等を踏まえ、既にペイメント事業戦略は柔軟に一部リプランしており、短期的にはライトニーズへの対応を進めながら、クレジットSaaSの営業活動を継続する等、引き続き「PAYCIERGE」全体での面展開による事業拡大を目指していきたいと考えています。
新グループビジョンについて
“社会に、多彩に、グローバルに” 価値を提供します。
「グループビジョン2032」では、“社会に、多彩に、グローバルに”をテーマとしています。引き続き、社会課題の解決には取り組みますが、「社会に」の意味合いが、仕事で“社会に”貢献することは当たり前だという考え方に変わってきています。「多彩に」と「グローバルに」は多様性を示し、多様な人材から多様なビジネスを生み出し、多様な価値・選択肢を社会に提供すること、同時に「グローバルに」は、日本に限定することなく、東南アジア市場を中心としたグローバル企業を目指す意思表明でもあります。
上記のテーマを踏まえて、「グループビジョン2032」では当社グループが注力する事業領域を示す戦略ドメインを一部見直しました。創業以来、受託型開発等を通じてお客様の事業をしっかり支援することで、ストラテジックパートナーシップビジネス(SPB)を収益の柱として確立してきました。また、「グループビジョン2026」においては、先回りによる提案型ビジネスとしてIOSを立ち上げる等、戦略ドメインを軸とした構造転換を進めてきました。今回、ビジネスファンクションサービス(BFS)をIOSに統合し、名称もIT&ビジネスオファリングサービス(IOS:略称は変わらず)と改めましたが、業務を含めたサービスを提供することでIOSが第2の柱となるよう成長の加速を目指していきます。さらに将来を見据えた第3の柱の土台となるビジネスが生まれるように、これまでのフロンティア市場創造ビジネス(FCB)を見直し、新たに当社グループが直接的に社会課題にアプローチするソーシャルイノベーションサービス(SIS)、共創するビジネスパートナーとビジネスを促進するコ・クリエーションビジネス(CCB)を加えた4つを戦略ドメインとしました。
戦略ドメイン比率を2024年3月期の48%から2033年3月期には80%に引上げ、多様なビジネスがバランス良く組み込まれた事業ポートフォリオを目指すことで、当社グループが社会に対して際立つ存在感を示せるだけの成長が実現できると考えています。
新戦略ドメインは社会的課題への直接アプローチと 共創がテーマです。
近年は、当社グループが直接的にITで社会課題を解決する取り組みも増え、同時に異業種を含むビジネスパートナーとの共創も増えつつあります。そのような状況の中、より大切なことは自分たちがどのように社会とつながっているかを考えることであり、その結果として新しいビジネスが生まれます。SISとCCBを戦略ドメインとして具体化したことや、社会課題解決型事業の新規創出・推進強化を目的としたソーシャルイノベーション事業部を新設したことは、社会課題と共創を軸とした事業の発展を目指すための仕組みづくりの一環です。
当社グループはサステナビリティ経営におけるマテリアリティ(重要課題)をもとに当社グループが貢献する4つの社会課題「金融包摂」「健康問題」「都市への集中·地方の衰退」「低・脱炭素化」を特定しています。これら4つの社会課題に対しては特定の戦略ドメインにおいてのみ取り組むものではありません。例えば「金融包摂」というテーマに対しては、金融系のお客様に提供する基幹システムの構築をSPBとして取り組みますが、IOSの中核となる「PAYCIERGE」の提供や、SISやCCBで取り組むようなMaaSや地域通貨等のサービス提供も含まれます。どの戦略ドメインが起点となるかに関わらず、社会やお客様に提供したい新しい価値を考えることがスタートで、社内外と連携しながら社会課題の解決を目指すことが何よりも重要だと考えています
新中期経営計画について
未踏の地を進むフロンティア開拓を基本方針に掲げました。
2024年4月からスタートした中期経営計画(2024-2026)ではフロンティア開拓を基本方針に掲げています。
私は2021年4月に社長就任以来、フロントライン強化の大切さを従業員に伝えてきましたが、フロンティア開拓とはフロントライン強化からつながる言葉であると同時に、未踏の地を進む、新規事業への挑戦をより強く意識した言葉でもあります。従業員には折にふれて未来は自分たちが描いて、自分たちで開拓していくしかないと伝え続けていますが、ITを通して社会にどのように働きかけていきたいかを能動的に考える人材が中期経営計画(2024-2026)での飛躍を実現すると期待しています。
IOS、モダナイゼーション事業、グローバル事業が事業成長における重要テーマです。
中期経営計画(2024-2026)の3カ年で達成すべき事業上のテーマは3つ、IOSの収益性向上、モダナイゼーション事業、グローバル事業です。前中期経営計画期間で複数の大規模開発プロジェクトがピークアウトし、この先は短期的にはやや成長角度が緩やかになる局面に入りますが、3つのテーマに徹底的に取り組むことが、さらにその先の事業成長と収益力強化につながると認識しています。
-
IOSの収益性向上
既にIOSは一定レベルの売上規模にまで拡大していますが、この3年間で収益面でも第2の柱として確立することを目指します。これまでIOSの中核である「PAYCIERGE」は様々な領域に積極投資し、機能を拡充することで進化を続けてきました。今後についてはクレジット/デビット/プリペイドなど、これまで売上成長期にあったサービスが2027年3月期に向けて収穫拡大期に入ると想定しており、売上成長の継続に加えて投資をしっかりコントロールしながら収益を確保・増大していく流れをしっかり作っていきたいと思っています。
また、2023年4月にグループインした日本ICS株式会社は非常に多数の中小企業をお客様に抱えています。これまで当社グループがSIでご支援してきた大規模なお客様だけでなく、より幅広い層へリカーリング型ビジネスを提供することで収益性向上につなげるとともに、最終的には我々の強みである決済領域において、将来のデファクトスタンダードとなりうるサービスの提供を目指します。 -
モダナイゼーション事業
経済産業省の『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』でも指摘されているように、技術者の高齢化による人材不足や最新のビジネス要請との乖離などを理由としてメインフレームのオープン化は多くの企業で喫緊の課題となっています。メインフレームを使い続けることは、メンテナンスコストの増大だけでなく、業務改善スピードの低下や新たなビジネスチャンスへの参入遅延等、将来の経済的損失につながりかねません。お客様が直面しているこのような課題に対して、当社が独自開発して一部要素では特許を保有する「Xenlon~神龍モダナイゼーションサービス」は短期間に安全かつ確実にモダナイゼーションを実現するツールとして高い評価をいただいています。COBOLなどのレガシー言語からJavaへの移行に関しては100%近い変換率を誇るだけでなく、変換後の高い保守性を確保し、動作時の性能も考慮したソースコードを自動生成できることが強みです。既に金融系および産業系のお客様においてメインフレームで稼働する大規模なアプリケーションのオープン化を安全・確実に遂行した実績が多数ありますし、マイグレーション後も根幹先として継続的にお取引いただいているお客様もいらっしゃいます。通常ですと、新規のお客様との信頼関係を構築し、戦略パートナーとして認めていただくには20-30年というくらいの長い年月がかかりますが、Xenlonは新たな根幹先となりえる新規のお客様の信頼を一気に獲得できる強力なソシューションだと大いに期待しています。 -
グローバル事業
当社グループは「ASEANトップクラスのIT企業連合体」の実現に向けて、2026年に連結売上高1,000億円を目指しています。これまでASEANを中心に、チャネルとテクノロジーの軸、後にコンサルティングの軸も加え、現地市場シェアの高い企業や高いテクノロジーを保有する企業との資本・業務提携を活発に行ってきました。この結果、2014年には40億円程度だった連結売上高も2023年には336億円、持分法適用会社等を含めた事業規模としては既に1,000億円超える規模にまで成長しています。なお、2026年にはオーガニックグロースで連結売上高400億円程度を想定していますので、目標達成のためには今後も事業投資を戦略的に行うこととなります。投資先を決定する際には当社グループのグループ基本理念「OUR PHILOSOPHY」に賛同いただけるかもポイントです。グローバル事業に限らないことですが、同じ価値観を共有できるかどうかが提携後の成否を左右する重要な鍵の1つと考えています。
一方で、グローバル事業の収益性はグループ全体と比較するとまだ低く、改善余地は大きいと見ています。引き続き日本のノウハウを東南アジアのグループ会社に導入することで経営効率を改善する等、収益性を高めるための取り組みを積極的に推進してまいります。それによって、彼ら自身が成長分野に対して投資ができるようになり、さらにグローバル事業の成長が加速する、そうした善循環を実現していきたい考えています
さらなる収益性向上を目指してPH営業利益、 ROICを追加しました。
中期経営計画(2024-2026)では、重要経営指標として売上高6,200億円、営業利益率13.1%、ROE16%超、EPSのCAGR10%超とともに、初めて一人当たり(PH)営業利益350万円超、ROIC13%超を掲げました。当社グループはこれまで、収益性を意識した経営のもと、着実に業績を伸ばしてきましたが、さらなる収益性向上には従業員一人当たりの収益性が鍵だと考えています。
PH営業利益については従来から社内では管理していた指標ですが、社外にもコミットメントする意味で重要経営指標に加えました。現時点では、先行投資型のサービス事業の立ち上がりが十分でないオファリングサービスや人手を介する単純なオペレーション業務の提供を少なからず含むBPMは一人当たりの指標が相対的に低い水準にありますが、今回の戦略ドメイン見直しで、業務とサービスの結びつきを強めて付加価値を高めることで、収益性の向上が実現できると考えています。
また、ROICについてですが、当社グループは従来のシステム開発に留まらず成長のための先行投資をする場面が増えてきました。そういった中では、より投資効率のよい事業を成長させていくという考え方が重要で、きちんとPDCAを回して管理していく必要があります。これまでも資本コストを意識した経営を重要視してきましたが、資本構成の影響を受けないROICを採用することで事業そのものの収益性に対する意識をより一層高めていく考えから設定したものです。
長期的な成長に向けて
リスクに的確に対応しつつ、変化をチャンスと捉えて 事業に邁進します。
長期的な成長を実現していく過程では、人材の流動リスクや情報セキュリテイ、自然災害や地政学リスク、様々なリスクが想定されます。また、当然のことながら新しい挑戦にはリスクが伴います。想定しうるリスクは全て事前に対応を準備する、その一方で想定し得ないリスクについてはいたずらに不安視せず、リスクを最小限に抑えつつも、新しい機会を最大限に活用するしかないと考えています。リスクとチャンスどちらに捉えるか、それは自分たちの考え方次第です。例えば、生成AIをはじめとする新しい技術については当社グループのビジネスにマイナスの影響を与えるケースもあれば、サービスへの組み込みによるビジネス拡大や、生産性向上によるコスト削減など、大きくプラスの方向で貢献する可能性があり、対応を進めています。また、ヘルスケアやロボティクスなど、実証実験等を継続する分野においては新技術にいち早く対応しながら、新規事業の創出と確立に取り組んでまいります。
一人ひとりの人間力が高い集団を目指しています
当社グループにおいては長らく構造転換をテーマに従業員の意識改革にも取り組んできました。近年のビジネスの進め方を見ると、私が事業部を率いていた10年前にこうあるべきと指向した方向に着実に進化し、コンサルタントを交えた提案型ビジネスや、社内外との連携が当たり前となりつつあります。当社グループの人材に必要なのは、ITビジネスにおける技術力、構築力、運用力、これらはベースとなる必要条件ですが、加えて重視するのが人間力です。お客様とのコミュニケーションを通じて本質的な課題を見抜く力があり、最終的にはお客様やビジネスパートナーから、もう一度一緒に仕事がしたいと言っていただける人間力が強い集団でありたい、これこそ漢方薬と同じで一朝一夕に成し遂げるものではありませんが、そのように言い続けています。我々の仕事は人材が最も重要な経営資本であることは間違いありません。仕事ができるのは当たり前ですが、その上で私が従業員と一緒に実現したいのは人間的な魅力のある集団になることであり、それが強固な経営基盤や長期的な成長の礎になると考えています。
ステークホルダーの皆様へ
次の事業の柱を確立し、次世代につなぐことが 私の役割です。
2021年4月に社長に就任して以降、私自身がフロントライン強化の先頭に立ち、当社グループの顔として多くの経営トップの皆様とお会いすることを心がけてきました。当社グループを知っていただくことで、現場が少しでも仕事がやりやすい環境となるよう、今後もフロンティア開拓の意識のもと、ステークホルダーの皆様とのエンゲージメントを継続かつ深化させてまいります。
中期経営計画(2024-2026)発表の際にもコメントしましたが、これからの3年はこれまでのように順調な事業環境が約束されているわけではありません。大型案件のピークアウト後の再成長をはじめ、対処すべき課題が多いことは変わりませんが、それらの一つ一つに対して真摯に向き合い、難しい局面を打破して成長していくのだという強い意志・決意のもと、目標達成に向けてやるべきことに対して徹底的に取り組んでまいります。
ITがますます社会で不可欠な存在となる今後に向けて持続的な成長を続けるべく、次の事業の柱を確立し、次世代につなぐことを私の役割として取り組んでまいる所存です。ステークホルダーの皆様には、より一層のご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
2024年9月