コーポレートガバナンス座談会
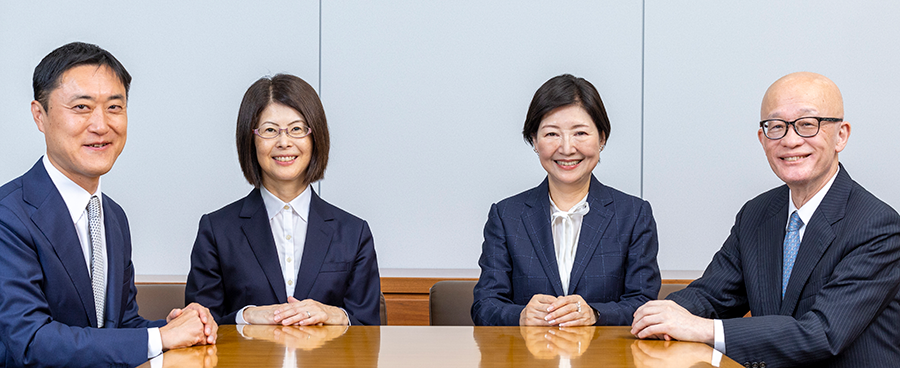
写真左から順に、円谷 昭一:一橋大学 教授(ファシリテーター)/水越 尚子:社外取締役/須永 順子:社外取締役/桑野 徹:取締役会長(取締役会議長)
当社グループは、持続的な企業価値向上を目指し、コーポレートガバナンスの高度化に継続的に取り組んでいます。実効性ある議論と意思決定を通じて、さらに経営の質を高めるべく歩みを進める中、本座談会では、取締役会議長と社外取締役に話を伺いました。
取締役会のミッションと現状認識
Q.取締役会のミッションと現状についてどのように認識されていますか。

円谷 :まず、現状の取締役会について、「企業価値向上に向けた実効性あるガバナンスの確立」といったコーポレートガバナンスの理想像を「山の頂」とすると、現在どのあたりまで登ってきたとお感じですか。

桑野 :取締役会の役割は当社グループの企業価値を向上させることです。そのために監督と執行の分離を推し進めるとともに、社外取締役が指名・報酬委員会委員長を務めることで透明性あるプロセスを確立するなど、当社のコーポレートガバナンスは一定の進化を遂げてきたと自負しています。しかし、現状は五合目にたどり着いたばかりとも言えます。ここまでは、コーポレートガバナンス・コード等の社会の要請に応えることに主眼を置いていたこともあり、やるべきことは多いながらも比較的明確でした。言わば、舗装された道を登ってきたようなものです。しかし、ここから先は自ら進むべきルートを見つけ、主体的に実行していく必要があります。変化の激しいIT業界で成長し続けるには、自ら課題を見つけ解決する姿勢が不可欠であり、ここからはこれまで以上に大変だと考えています。

水越 :2018年に私が初の女性社外取締役として就任した当時は会長と社長が兼務しており、ややもすると取締役会の議論が社内の論理に押し切られるリスクも高かったように思います。当時は五合目にも届いていなかったかもしれません。ただ、その後の改革で社内取締役の意識も格段に変化し、山の六~七合目ぐらいまで登ってきたという実感があります。ただ、社外取締役の比率やスキルの多様性という点ではまだ改善の余地があり、さらなる高度化のために登るべき部分が残されていると感じています。

須永 :私も五合目という認識です。私が2024年に就任した時には、既に「グループビジョン2032」や中期経営計画(2024-2026)の枠組みは整っていました。しかし、目指すところへ本当に到達できるか、その道筋がまだはっきり見えない部分があるため、取締役会で執行側と議論を重ねていく必要があります。頂上まであと半分あるという意味で五合目だと感じています。
取締役会の雰囲気と実効性
Q.取締役会の雰囲気について教えてください。また、実効性向上のための課題はありますか。
円谷 :一言で表すと、御社の取締役会はどのような雰囲気でしょうか?
水越 :社外取締役は忌憚なく発言でき、実際に発言しています。その意見は真摯に受け止められており、株主等ステークホルダー視点を踏まえた社外取締役の意見を無視すること自体がガバナンス上の問題であるという認識が広がってきていると感じます。一方で取締役会の実効性評価でも言及されていますが、社内取締役にも大いに発言してほしいですね。
桑野 :執行を兼務する取締役が、担当組織の長としてではなく、グループ全体の経営責任者の一人として発言する意識がまだ不十分であることは課題の一つです。社内取締役が執行側の意見になりがちなのはある程度仕方がないと割り切って、社外取締役の人数やスキルの多様性を高めていくのか、考えるところですね。
須永 :私も当社の取締役会は「自由であり真面目である」という印象で、非常に健全だと感じています。社外取締役の意見を真摯に聞いていただけると感じており、実際に社外取締役の反対意見を踏まえて議論し、執行側が議案の上程を取りやめた事例もあります。執行を兼務する取締役は、自身の担当ビジネスを成長させるミッションもあるため、グループ全体での自由闊達な意見交換が難しい場面もあるかもしれません。だからこそ、指名委員会等で経営陣を決めるサクセッションプランの策定・監督がより重要になると考えます。
円谷 :社内取締役の意識をより「取締役」として高め、グループ全体の視野で議論すること、そしてそのためにサクセッションが重要であるというご指摘、よく理解できました。
資本効率と人的資本経営で挑む企業価値向上
Q.取締役会では、P/Lだけでなく資本効率に関する議論も行われていますか?
また、市場からの評価をどのように捉えていますか。
円谷 :企業価値の向上が強く求められる中で、資本効率の改善は避けては通れないテーマだと思います。株主視点で重視される資本効率についての議論も、取締役会の中では頻繁に行われているのでしょうか。
水越 :当然行われています。以前は営業利益率などP/L中心でしたが、ここ2~3年でB/Sマネジメントとして資本効率に関する議論が強まってきました。そうした流れから今では定期的に資本政策を含めた議論をしています。
須永 :機関投資家との対話でもROEなどの経営指標に関する質問が非常に多いこともあり、取締役会でも重要な指標として一層注目度が高まっていると感じています。
水越 :議論の進化の過程は大きく3段階に分けられます。当初は営業利益率の低い事業の改善、構造改革が議論の中心でした。次に政策保有株式や不要資産の売却などROA改善の視点が加わり、現在は投資家との対話も踏まえ、B/Sマネジメントや資本コストを意識した議論に進化しています。
桑野 :当社グループの資本政策はある程度評価されつつあると認識しています。問題は、いかに成長戦略を明確にし、それが計画通りに進んでいることを外部に示せるかが少し見えにくくなっていることだと感じています。最近の当社PERが業界平均よりも若干劣後しているのは成長戦略が不十分か、外部から見て不透明に映っている可能性があると考えており、取締役会として懸念しています。そのため、成長戦略に関する議論により多くの時間を割けるようにアジェンダ設定等も工夫しています。
水越 :変化の激しい業界で、市場は「当社グループが継続して選ばれ続ける存在なのか」を見極めようとしています。ガバナンス面の強化は大事です。他方、実体的な成長が不可欠です。M&Aや海外戦略、事業ポートフォリオのストーリーがまだ市場に伝わりにくい、あるいは中身そのものの強化・深化が必要かもしれません。
桑野 :企業価値創出の源泉である従業員の価値も高めていく必要があります。人材を増やさずに収益を上げるため、サービス型のビジネス、人材への投資、パートナーとの関係性強化などは、経営効率を高める上で非常に重要なテーマなので、当社グループとしてどういう方針をとるべきかを執行側だけに任せず、取締役会としても積極的に関与すべき領域です。
Q.人的資本経営についてどのように議論されていますか。
円谷 :一人当たりの生産性や収益性を高めるための人的資本経営についてはどのような議論がされているのですか?
須永 :中期経営計画(2024-2026)の中でも、人的資本強化のための積極的な投資を計画しています。日本では海外よりも新卒を重視しており、教育や処遇改善といった人材の付加価値を上げていくための議論や投資は十分行っている印象です。
水越 :適材適所への人材配置はどの企業も苦労していますが、当社グループが人材戦略でリーダー的な地位を築き、それを社内外に示すことは、優秀な人材の獲得にもつながると考えています。
株主との対話と企業価値評価
Q.機関投資家との対話ではどのような気づきがありましたか。
円谷 :機関投資家との対話を実施されていると伺っていますが、対話においてどのような質問を受け、どのような感想をお持ちになりましたか。
水越 :中期経営計画(2024-2026)のKPIとしてコミットしている資本効率性や、役員報酬におけるインセンティブ設計、成長戦略のモニタリングなどに関する質問が多かったです。また、社外取締役の重要性から比率を高めるべきだというご意見も印象に残っています。
須永 :長期的な目標であるROE20%水準の達成に向けたアプローチについても関心が高く、過剰な資本はもっとコントロールすべきという提案をいただきます。当社グループもその方針です。ROEの分母となる自己資本を圧縮することだけで資本収益性を高める企業も海外では見受けられますが、分子となる利益を増やすための事業成長を軽視すべきではありません。また、アセットライトということで不要な資産は持つべきではないということはその通りだと考えていますが、一方でご指摘いただくことのある賃借から取得に切り替えた運用業務等における中核施設についてはお客様の情報資産を守る社会的責任から例外的措置として現時点では保有すべきものだと考えており、対話の中でもお伝えしてご理解いただくように努めています。何よりも大事なのは企業としての実力値を高めていくことであり、その前提のもとで公正かつ機動的に資本政策が実施されるよう監督することが重要です。
Q.企業価値を何で測るべきだと考えますか。
円谷 :近年の日本ではアクティビストによる買収・株主提案が活発化する中で、自社の適正な企業価値やその市場評価と言える時価総額の目標値についての議論はありますか?
水越 :株主が株価の上昇・時価総額の拡大を求めるのは当然であり、私たちも理解しています。時価総額についてはモニタリングしていますが、直接目標にすることには、短期的な株価上昇手段に囚われるリスクも潜むため慎重な議論が必要です。ただ、株価を意識した経営をしつつも、健全な成長に伴って株価が上がることが、経営の安定性確保・向上において最大のポイントであることは間違いありません。
円谷 :普段から、時価総額を含めてアクティビストを含む機関投資家の考え方を社内取締役も含めて理解し、ファイナンスリテラシーを高めておくこともあらぬ事態を招かない条件の一つかもしれませんね。
須永 :ファイナンスリテラシーは経験を積むことで高めることができますし、アクティビスト等の視点を知ることはガバナンス強化にもつながります。一方で、社外からの提案は時に短期的視点に基づく場合も多いため、グループ基本理念「OUR PHILOSOPHY」を基盤に、持続的な企業価値向上を念頭に置いた企業活動を行っていくという基本は忘れてはいけないと思いますね。
指名・報酬委員会の取り組み、今後のガバナンス強化について
Q.指名・報酬委員会の取り組みと、今後のガバナンス強化について教えてください
円谷 :取締役会の体制づくりにおいて指名・報酬委員会の果たす役割は非常に大きいと思います。2025年3月期に委員長を務めた水越社外取締役からどのような観点を重視して運営されているのかお聞かせください。
水越 :指名委員会の大きなミッションの一つはサクセッションプランの策定です。次期経営トップについては変化が激しい時代に合ったリーダー像を確認し、透明性のあるプロセスを経て選定することを重視しています。社外取締役については多様性の観点、社内取締役についてはグループを牽引できる人材であるかを中心に議論しています。また、議論の対象は取締役会メンバーに留まらず、グループ会社の取締役、中核会社の執行役員にまで範囲を広げています。報酬委員会では近年、1年半ほどかけてしっかり議論した上で役員報酬制度を改定し、業績連動比率を高めました。
円谷 :2024年3月期は指名委員会が8回、報酬委員会が6回と他社と比べて開催頻度が多いですね。
水越 :報酬改定やサクセッションプランなど重要なテーマを議論する際には自然と開催回数は多くなりますね。そこに時間と労力を惜しむべきでありません。
須永 :一方で、取締役会に上程するアジェンダは見直しを実施しており、中長期の成長に向けて重要な議案により多くの時間を割いて議論するようになりました。こうした取り組みにより取締役会の効率化・高度化は進んできていると思います。
桑野 :取締役会の議長としては、取締役会当日の進行だけでなく、どのような議論が必要か、執行側が説明すべき重要なポイントをもらさないようにコントロールすることなども含め、大きな役割を担っています。今後、ガバナンスの一層の高度化に向けては、社外取締役の増員や、社内の執行兼務取締役の人数や役割、そして私のような非執行の社内取締役の位置付けといった点も議論していく必要があります。指名・報酬委員会では、トップだけでなく、幹部層のサクセッションプランも重要で、これは各々に関わる話なので難しい側面があります。議論すべきテーマはまだ多く、これが五合目だと申し上げた理由の一つでもあります。
これからの取締役会の役割と対話の先に描く未来
円谷 :皆様のお話から、御社のガバナンスが着実に進化をしていること、そして持続的な企業価値向上への強い意思が感じられました。一方で、コーポレートガバナンスのさらなる高度化の必要性については共通認識かと思います。今後のガバナンス高度化に向けて一言ずついただけますか?
水越 :就任後、取締役会を支える制度や仕組みは大きく成長したと感じています。しかし、事業ポートフォリオやサービスごとの成長ストーリーがまだ分かりにくい部分があり、取締役会としてさらに検討できる余地があると感じています。現在、2年ほどかけて、当社グループのガバナンスを次のステージに進めるべく議論を重ねており、取締役会の実効性をさらに高めていきたいです。
須永 :まずは中期経営計画(2024-2026)のKPIを確実に達成することが、株主の負託に応える基本です。実際に機関投資家との対話から得られた気づきを経営に活かし、成長戦略の実行状況をしっかりモニタリングすることで、企業の実力値が高められるように貢献していきたいですし、その結果として市場からの評価・期待が高まり、株価が上がったと説明できる状態を目指します。
桑野 :2011年にTISがグループ内で3社合併した際には、当時社長として組織づくりなどに奔走していました。合併直後はやるべきことが明確だったため必死に取り組む日々でしたが、数年後にそれらが一通り落ち着くと、今度は自ら何をすべきか考え実行する段階に入り、そこからがもっと大変だったということを思い出しました。冒頭で申し上げたようにコーポレートガバナンスの高度化も同様で、これまではやるべきことが比較的明らかでしたが、今後はまさに「自分たちで何をすべきか考える」フェーズに入ります。取締役会のかじ取り役である議長として、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に資する、実効的かつ建設的な議論を促進していく所存です。これからが当社グループのコーポレートガバナンスを進化させる本番といえます。
円谷 :本日の議論が御社のコーポレートガバナンスの一層の深化、そして企業価値の持続的な向上につながることを期待しております。
2025年9月
